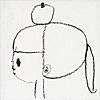潮汐(Tide)
夢のくぐり方を間違えた。まだ空も白んでいない、早い時刻に目覚めてしまった。起き抜けのぼんやりした頭。布団の上のナマケモノ。薄暗い中で、枕元のペットボトルに手を伸ばす。唇のすき間から、そして汗腺から逃げていった水分を補いたい。日照りの町が雨を乞うみたいに。口をつけ、ゆっくりと傾ける。思いのままに飲みつづけた。路上の花が静かに雨を享受する。そうして潤いを取り戻した身体は、ふたたび眠りに落ちた。
昔からの僕の悪い習性で、いったん欲しいと思ってしまうとしばらくそのことで頭がいっぱいになる、というのがある。服や音楽、甘いもの。すっかり美化されて、何をしていても焦点がそちらの方へ流れていく。欲望はこわい。囚われてみるとなかなか抜け出せない。そして実際に買ってみると案外大したことなかった、というのはいつものことだ。自分が勝手に作り出した幻想は、叶ってしまうとすっかり色をなくしてしまう。このおかげで、僕はどれくらいのお金を費やしてきたんだろう。いや、あんまり考えるのはよくない気がする。血眼になって何かを求めている自分は、狂っているし何しろ情けない。
朝に潤った喉は、午後にはもう渇いている。僕は潮のことを思い浮かべた。どこかで潮が引いているあいだ、違うどこかで潮が満ちている。海水がせっせと移動している様子を想像すると面白い。それはどこか、二人の人物に恋してしまった人の忙しい日々みたいだ。朝食を一緒に食べながらにこやかにお喋りしていると、もうランチの予定が迫っている。それらしい嘘を残して席を立つ。からからの砂浜と、満ち満ちた海洋。
見慣れた夜が来た。ペットボトルに残った水。コップ一杯分ぐらいだけど、明日の朝のために置いておこう。頭の中でにわかに、こんな服欲しいなあと誰かが絵を描いている。僕自身が欲しいと思っているのか、よく分からない。ああ、僕らの海は今頃どうなっているんだろう。干潮か、満潮か。今このときも、気づかないうちに渇き始めているのだ。どんどん、世界中から。
ゆふれゐ
本屋。興味のある雑誌を手に取って紙を捲っていると、後ろに人の気配を感じる。見えないけれど確かにいて、見えないゆえに気になってしまう。雑誌の内容が頭に入らない。捲る手を止め、本を閉じる。それを元の場所に戻すと、さささと去る。妙に身体が重い。人とすれ違うだけでひどく神経を消耗して、疲れる。そうして外へ出てみれば、今度は無邪気な熱に構われて、気がつくと汗が噴き出ている。シャツが肌に張り付く。
最近、肉体がなければどれだけ便利だろうと考える。皮膚も性器も髪もない。衣服も住所もたぶん必要ない。魂だけが町を泳いでいく。あらゆる責任を放棄した姿はずいぶん楽そうで、水のように軽やかに思える。いや、こんなこと考える自分はちょっと疲れているのかもしれない。だけど気分転換に外に出ると汗だくになって憂うつな気分を覚えるし。家にいたって退屈極まりない。TVを見ると息をするのも苦しくなる。ラジオ番組は深夜になるまで面白くない。八方塞がりだ。
時どき、自分が幽霊のように感じるときがある。いるのにいない。「死んだ者」として眺めているような感覚。光を浴びて人間を演じる彼らを、舞台袖の薄暗がりから見つめる幽霊。物語の終わりを予感しながら、ただそのときを待つだけの存在。死んだ、遅れた者だからそれしかできないんだという虚しさと、ステージでの狂騒と距離があることへの気楽さ。物語よ終わるなと叫びつつ、その内実では「さっさと終わってしまえ」と思っている幽霊。
肉体はあまりに多くのことを魂に付加してしまう。面倒だなと思いつつ、仕方がないとため息をつく。いつか本当に幽霊になってしまうまで、肉体を労らなければならない。現在地に縛られ、キッチンから漂うひどい臭いに悩まされ、強い風で簡単に吹き飛ばされてしまう。それでも肉体が行なった一つ一つが、僕を残していく。僕がいなくなったとき、部屋に、そして誰かの頭に残ったすべてが、僕を再び作り出す。いないのにいる。それが幽霊。
健やかなる
いつの間にか、凝った料理を見ると「誰が作るんだろう」と思うようになってしまった。入念な下ごしらえ、丁寧な調理。そもそもこれだけの食材と調味料を用意するのにいくらかかっているんだろう。余計なことばかり気になって料理がおいしいのかはどうでもよくなっている。でも、凝った料理をする余裕のある人が日本にどれくらいいるのかは正直気になる。
雑誌で見た、仲の良い人と一緒に料理を作ってそれらをつまみながら映画を観る、というのが頭から離れない。一人でただ自分のためだけに虚しくキッチンに立つより、効率も気分も上がる。しかもその中に写っていたフェットチーネのカルボナーラがたまらなくおいしそうで、フォークがドレスを纏うようにくるくると巻き、口の中へ運ぶところを想像するとお腹が哀しく鳴った。僕と味覚や映画の趣向が合う人はいるのか分からないけれど、人生で一度はこういう経験がしたい。休日、友人を家に招く。この日のために汗水垂らして掃除した部屋。磨かれたキッチン。味覚の充足という一つの目的に向かっての協働。
それにしても、健康ってなんだろう。煙草を何十年も吸い続けて元気な人だっているし、逆に身体を害する人もいる。僕は気管支が弱いから煙草は吸わない。どちらかといえば健康的な生活を送っているような気がする。それでもときどき食べたくなる。こってりとした、いかにも身体に悪そうなジャンキー・フード。アメリカの食産業の奴隷だ。いくらかの罪悪感と、抗えないおいしさを抱く。僕はその間、寿命だとかそういう概念を忘れる。あむあむするだけだ。
僕らが本当の意味で健やかな生活を送るためには、たくさんの問題に立ち向かわなければならない。それはどんな手の込んだ料理よりもうんと面倒で、いくつもの手順を踏む必要がある。たくさんの人がテーブルを囲い、あれこれ喚き立てる中で、全員が納得する料理を作るような難しさ。でも、一つ一つ乗り越えていけばきっと見つかるはず。みんなと言葉を交わし、みんなを尊重し合い、一つ一つ探っていけば。テーブルをたくさんの食器で彩って、くちゃくちゃむにゃむにゃ言わせながら、映画でも観よう。『グッドナイト・ムーン』って映画、僕のおすすめだ。
やがて冬が
夜がだんだん早く来る。この窓から見える山の色も、近いうちに移ろいゆくはず。人々が身にまとうものも変化しはじめて、または新しい季節へ歩みだす。次の月へ、次の年へ。そして切ない鐘の音が鳴る。何も変わらぬまま、しかし沢山のことが変わってしまったまま。
人は何でも想定する。この事業はどれくらい成功が見込めそうか、この人と結婚して自分は幸せになれそうか、地震が来たときにどこへ避難すれば安全そうか。人は想像し、計算して、予測を立てて物事に対処する。それによって危機を脱したり、あるいは臆病になったりする。農家の息子は自分が百歳まで生きることを考え、畑を置いて街へ出る。そういうこともあるかも知れない。これを読みながら、あなたも考える。果たしてこの文章は面白いのだろうか、と。
親を見て、大人たちを見て、僕は将来の自分を想定する。例えば髪が薄くなり、腹が出て、情けなくなった姿。どんな仕事を就いているかは分からない。一日中清掃をしている可能性だってある。大きくなっていく過去と夜毎減っていく未来。雑巾をしぼりながら洗面台に向かって何か嘔吐したくなる。酒だけが自分に優しくしてくれる夜。同世代の人とすれ違うたびに、自分がどの分岐点で間違えたのか途方に暮れる。冬。次の季節に何を残せるだろうか。そうして掌を自分の息で暖める。
もちろん嫌なことばかりじゃないだろう。素敵な人と出会って、その人とおいしいものを食べ、安らぎと快楽を感じ合う。そんな輝かしい夏の日がいつか来るはず。まぶしい太陽とひどい雨風を受けて果実はますます甘みを増していくのだから。今はただ冬を恐れるしかない。イソップ物語に出てきたアリのように、せっせと働いて厳しい冬に備えるのだ。ときどきキリギリスのように堕落しながら。やがて来る冬を受け入れよう。家の中へ招いて、一緒にそばでも食べよう。そして鐘の音で、なにもかも忘れてしまうのだ。
沈黙は優しい
虫の音が気持ちいい。秋の予感がする。明るいような、さみしいような音色。夜になっても、町のどこかで生活の音がすると安心する。いろんな音、涼しい風が網戸から入りこんできて、僕の耳や素足に絡みつく。甘くふくらんだ夜の空気。僕はあくびをする。もう後は布団に入って大人しく瞳を閉じるだけだ。
四六時中ってわけじゃないけれど、ときどき君を思い出して電話がしたいなあと思う(お風呂に浸かっているときや歯磨きしているときなんかに思う)。特に話したいことはないはずだ。それでも長引く沈黙を畏れて、訳の分からないことを喋ってしまう気がする。君の方は黙っていても平気だと言った。沈黙を延期するのはだいたい僕の方だ。もちろん、二人の間で静寂を共有しているのも悪くはない。今ならきっと、君の耳元で虫の音がしているはずだ(リンリンリン)。
沈黙はかなり重苦しい。でも同じくらい優しい。何も言葉を交わさなくても満たされる関係。その素晴らしさに出会えることは滅多にない。いろんなコミュニケーションを払い除けて、閉口したまま横になる。僕が話題もないのに電話をかけたいのは、君と黙り合うためかも知れない。ただ、お互いの生活音を何時間も聞いていたら、きっと可笑しさで吹き出してしまう。だけどそんな関係を僕は愛でてみたい。
また町に戻れば、近所の喫茶店に行くだろう。メニューを注文するとき以外、ほとんど喋らず、コーヒーを啜って本を読む。大きな孤独が向かいの席に腰を下ろす。やがてジャズのレコードが止まって、しんと静かになる。別のレコードが回りだす。僕はこの至福を口にせず、顔にも出さない。でも何となく伝わっていればいいなと思う。こここそが孤独な人間の安らげる最適な場所だと。そろそろホットコーヒーの季節になる。
KIDS
家族三人で近所の道を歩く。夏の夕方、特別今日は涼しくて快い。鼠色の空からぱらぱらと小雨も降っていた。歩道橋を渡り、目当ての洋食屋に着くと、僕らは腰を下ろした。外で晩ご飯を食べるのなんて珍しい気がする。僕はオムライスを注文した。ふわふわの卵に、ほかほかの白米。心地いい満腹感。言葉を交わして、ほどよく豊かな午後を味わってお店を出た。夏の宵。町からにじむオレンジの灯り。時どき自転車が通り過ぎていった。部屋の重い扉を開けて中に入ると、途端に眠たくなった。うーん。
今日もそうだったけれど、お父さんはよく幻想を口にする。旅行がいい例だ。いつかあそこに行こう。笑顔でそう語る。僕とお母さんはもう馴れっこなので、また始まったと受け流す。家族で、どこか他県へ旅行したことなんて無い。だけどお父さんは、宝くじを買ったときや家族でご飯を食べているときなんかにふと旅行について語り出す。それは、冗談なのか、本気なのか。その時々によって違う気もするから、よく分からない。「嘘ばっかり」と二人が笑うのが面白いのかも知れない。お父さんも皺を寄せる。
そういえば今年、僕は二十歳になった。あんまり実感はない。だらだらとお酒を愉しんでいるだけだ。だんだんと社会というものが侵食しているのを感じているけれど、自分の情けなくてふがいない部分はまだ消えてくれない。夏の夜に名残る微熱みたいに。僕はいつまで、この子供を抱え続けるんだろう。もしもこの先、誰かと結婚していつか子供が産まれるとして、その時にはいなくなっているのかな。僕の親や周りの大人たちを見ていると、なかなか難しいように思う。この家にいる三人の成人は、一方でまだ子供だ。手のかかる、難しい子。
話は戻るけれど、僕は旅に出かけることよりも、家族とぶらりと近所を歩くことの方が本当は楽しい。靴を脱いで、あくびをしながら羽織っていたシャツをハンガーにかける。家族でテレビを観て、そのあとアイスクリームを口にする。くたびれた身体を湯船に預ける。明かりが消え、眠りにつく。今度は三人でお酒を酌み交わしたりなんか、してみようかな。ちょっと恥ずかしくはあるんだけど。
再上映
親がもう寝静まって、町全体も眠りについた。本当なら、僕もそういう状態でいなければならないのだろうけど、まだ目が冴えている。部屋の壁に備え付けられている、火災報知器が黄緑色の光を放っている。乱視の目でそれをぼうっと眺めていた。右へ左へと身体を動かして、眠れる体勢を探ろうとしてみるものの、やっぱり眠れない。布団を被って苦行のように熱の中で目をつむるけれど、ただ汗がシャツに染むばかりだ。
こういう夜に限って、今までの人生(大した思い出のない微かな人生だけど)をふと振り返ってしまう。頭の中で昔の記憶が上映される。何回目の再放送だろう。僕はその記憶の視聴者でありながら、同時に監督でもあるので、「ここのカットはこういう風にしよう」と勝手に変更を加えてみたくなる。本来の記憶とは違う、もしもの並行世界をしばらく楽しんで、そのあとやって来る虚しさと対峙する。あのとき自分がこう行動していれば今よりちょっとましな人生になっていたかもしれない、でもそれは今のやるせなさを誤魔化したいだけだ、とか。ただ空想したいだけなのに、なんだかそこに責任を感じてしまう。丸い汗がすうっと額を駆け抜ける。母親のいびきが炸裂する。
このところ大気が不安定で、日の光にうんざりしていると突然雨が降ったりする。簡単に移ろう天候に身体は疲れて果てる。それでも外へ出なければならない日々が待ち構えているので、僕はちょっと暗闇の冷たさにうっとりする。部屋に充満する暗がりの色。朝が来れば物陰に隠れてしまう。だから今だけは、この安全地帯で、それぞれのさみしさを持ち寄って語り合う。意味のない言語を使う。どちらかが眠ってしまうまで、布団の中で、ひそひそとだべり続けるのだ。間が持たないときは、映画でも流してみる。懐かしい人の、懐かしい映画を。