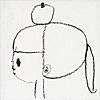沈黙は優しい
虫の音が気持ちいい。秋の予感がする。明るいような、さみしいような音色。夜になっても、町のどこかで生活の音がすると安心する。いろんな音、涼しい風が網戸から入りこんできて、僕の耳や素足に絡みつく。甘くふくらんだ夜の空気。僕はあくびをする。もう後は布団に入って大人しく瞳を閉じるだけだ。
四六時中ってわけじゃないけれど、ときどき君を思い出して電話がしたいなあと思う(お風呂に浸かっているときや歯磨きしているときなんかに思う)。特に話したいことはないはずだ。それでも長引く沈黙を畏れて、訳の分からないことを喋ってしまう気がする。君の方は黙っていても平気だと言った。沈黙を延期するのはだいたい僕の方だ。もちろん、二人の間で静寂を共有しているのも悪くはない。今ならきっと、君の耳元で虫の音がしているはずだ(リンリンリン)。
沈黙はかなり重苦しい。でも同じくらい優しい。何も言葉を交わさなくても満たされる関係。その素晴らしさに出会えることは滅多にない。いろんなコミュニケーションを払い除けて、閉口したまま横になる。僕が話題もないのに電話をかけたいのは、君と黙り合うためかも知れない。ただ、お互いの生活音を何時間も聞いていたら、きっと可笑しさで吹き出してしまう。だけどそんな関係を僕は愛でてみたい。
また町に戻れば、近所の喫茶店に行くだろう。メニューを注文するとき以外、ほとんど喋らず、コーヒーを啜って本を読む。大きな孤独が向かいの席に腰を下ろす。やがてジャズのレコードが止まって、しんと静かになる。別のレコードが回りだす。僕はこの至福を口にせず、顔にも出さない。でも何となく伝わっていればいいなと思う。こここそが孤独な人間の安らげる最適な場所だと。そろそろホットコーヒーの季節になる。
KIDS
家族三人で近所の道を歩く。夏の夕方、特別今日は涼しくて快い。鼠色の空からぱらぱらと小雨も降っていた。歩道橋を渡り、目当ての洋食屋に着くと、僕らは腰を下ろした。外で晩ご飯を食べるのなんて珍しい気がする。僕はオムライスを注文した。ふわふわの卵に、ほかほかの白米。心地いい満腹感。言葉を交わして、ほどよく豊かな午後を味わってお店を出た。夏の宵。町からにじむオレンジの灯り。時どき自転車が通り過ぎていった。部屋の重い扉を開けて中に入ると、途端に眠たくなった。うーん。
今日もそうだったけれど、お父さんはよく幻想を口にする。旅行がいい例だ。いつかあそこに行こう。笑顔でそう語る。僕とお母さんはもう馴れっこなので、また始まったと受け流す。家族で、どこか他県へ旅行したことなんて無い。だけどお父さんは、宝くじを買ったときや家族でご飯を食べているときなんかにふと旅行について語り出す。それは、冗談なのか、本気なのか。その時々によって違う気もするから、よく分からない。「嘘ばっかり」と二人が笑うのが面白いのかも知れない。お父さんも皺を寄せる。
そういえば今年、僕は二十歳になった。あんまり実感はない。だらだらとお酒を愉しんでいるだけだ。だんだんと社会というものが侵食しているのを感じているけれど、自分の情けなくてふがいない部分はまだ消えてくれない。夏の夜に名残る微熱みたいに。僕はいつまで、この子供を抱え続けるんだろう。もしもこの先、誰かと結婚していつか子供が産まれるとして、その時にはいなくなっているのかな。僕の親や周りの大人たちを見ていると、なかなか難しいように思う。この家にいる三人の成人は、一方でまだ子供だ。手のかかる、難しい子。
話は戻るけれど、僕は旅に出かけることよりも、家族とぶらりと近所を歩くことの方が本当は楽しい。靴を脱いで、あくびをしながら羽織っていたシャツをハンガーにかける。家族でテレビを観て、そのあとアイスクリームを口にする。くたびれた身体を湯船に預ける。明かりが消え、眠りにつく。今度は三人でお酒を酌み交わしたりなんか、してみようかな。ちょっと恥ずかしくはあるんだけど。
再上映
親がもう寝静まって、町全体も眠りについた。本当なら、僕もそういう状態でいなければならないのだろうけど、まだ目が冴えている。部屋の壁に備え付けられている、火災報知器が黄緑色の光を放っている。乱視の目でそれをぼうっと眺めていた。右へ左へと身体を動かして、眠れる体勢を探ろうとしてみるものの、やっぱり眠れない。布団を被って苦行のように熱の中で目をつむるけれど、ただ汗がシャツに染むばかりだ。
こういう夜に限って、今までの人生(大した思い出のない微かな人生だけど)をふと振り返ってしまう。頭の中で昔の記憶が上映される。何回目の再放送だろう。僕はその記憶の視聴者でありながら、同時に監督でもあるので、「ここのカットはこういう風にしよう」と勝手に変更を加えてみたくなる。本来の記憶とは違う、もしもの並行世界をしばらく楽しんで、そのあとやって来る虚しさと対峙する。あのとき自分がこう行動していれば今よりちょっとましな人生になっていたかもしれない、でもそれは今のやるせなさを誤魔化したいだけだ、とか。ただ空想したいだけなのに、なんだかそこに責任を感じてしまう。丸い汗がすうっと額を駆け抜ける。母親のいびきが炸裂する。
このところ大気が不安定で、日の光にうんざりしていると突然雨が降ったりする。簡単に移ろう天候に身体は疲れて果てる。それでも外へ出なければならない日々が待ち構えているので、僕はちょっと暗闇の冷たさにうっとりする。部屋に充満する暗がりの色。朝が来れば物陰に隠れてしまう。だから今だけは、この安全地帯で、それぞれのさみしさを持ち寄って語り合う。意味のない言語を使う。どちらかが眠ってしまうまで、布団の中で、ひそひそとだべり続けるのだ。間が持たないときは、映画でも流してみる。懐かしい人の、懐かしい映画を。
祭よ
暑いのに。肌が汗ばむ季節なのに。人はわざわざ町へ繰り出して群れをなす。その濁流はとても強大で、引き返すことは簡単じゃない。肩と肩がぶつかる。他人の湿った肌が触れる。さまざまな匂い入り乱れて、熱気がたちこめる。それでも人々は騒がしさの方へ誘われて踊りをおどる。
太鼓の音がする。胸の奥まで一気に届いて、心臓マッサージのように繰り返す。幼い頃、母に抱えられながら阿波踊りを観に行った日からこの感覚がなんだか苦手だった。吐き気のような、決して心地よくない振動。どれだけ強靭な肉体を手に入れたとしても敵わない。だんだんと気分が悪くなって、逃げるように本屋へ駆けこんだ。静かで人もまばら、すてきな空間で雑誌なんかを立ち読みしたり、吉田秋生の漫画を手に取ったりした。涼みに来る人もいたけれど、たぶん普段よりも客の数は少なくて、ずいぶん快適だった。
名残惜しい気持ちで外に出ると、燦燦と日が射していた。人々とすれ違う。浴衣を着た女性、その彼女と腕を絡ませる男性。着飾った女の子、その後ろを歩く父親らしき人。年齢も国籍もごった煮で、全員が祭に巻き込まれている。裏通りを歩いていると、本番を控えた踊り子たちが不安げな表情で休んでいた。遠くの方で、囃子が鳴っているのが聞こえる。
祭という文化には、どこか神話のような力を感じる。見えない手が人々を活気の中へ連れていき、僕たちの細胞が身体を揺らし、高らかに踊らせる。山の緑が夏の風に揺れるように。暑いのに、人がいっぱいで困るのに、祭は絶対に無くならない。いくらそれが商業化されたものでも、たぶん本質の部分は変わらない。人々が火を囲って踊りをおどっていたであろう頃からずうっと続いてきた野生的な感じ。これがずっと続いていくんだろうなあと、騒がしい町並みを歩きながら考えていた。僕はちょっと遠回りして鉄道に乗って帰ったけれど、夜遅くまで祭は終わらない。浮れ、酔っぱらって、ふらふらで。本当に、阿呆で不可思議な時間だ。
刺青 / TATTOO
夏は容赦ない。刀を鞘から抜き、せっせと刃を研いでいる。そして歩く人々に向かって一気に刀を振り下ろす。僕の肌は無茶苦茶に傷ついて、傷口から透明な血があふれ出す。からだ中から水分が逃げていく。拭うハンカチは汚れていく。視線はどうしても涼しい場所を探してしまう。大学の図書館はエアコンも扇風機も効いていない。自然と喫茶店へと足が向く。
夏に斬られたとはっきりと気づくのには、少し時間がかかる。ふっと席に腰を下ろして、何を飲もうかとメニューを見ているときに、額からぽたぽたと流れてくるのに気づく。焦ってタオルで拭く。アイスコーヒーを注文して、畳んだタオルでぎこちなく顔を仰ぎながら店の中を歩く。客は他にいない。お店の人との不穏な時間が流れていた。路面電車が何度か通った。小腹が空いたからジャムトーストも頼んで、それをぺろりと消化した。本当に長いあいだ居座ったと思う。新しいお客が来たのに合わせて、席を立った。
夏休みとは言っても、今年はほとんど休めなさそうだ。はあ、今日ここへ来たのだってほとんど逃避に近い。嵐の前の休息。本当の心はぼんくらもぼんくらだ。肩の部分に刺青を入れて、誰かと一晩中汗みどろになるときだけそれをひけらかして、昼の光を浴びるときは何食わぬ顔で眼鏡でもかけている、そんな心だ。そうだ、こっそり刺青をいれている人と友達になってみたい。風呂に浸かるタイミングで、その人の小さな赤い薔薇に触れて、なんでいれたの?とか訊いて。ちょっとした秘密を服で隠しているのが面白いと思う。そんな人と海に行って堕落したいけれど。
夏の空気にまた晒されて、来た道を帰る。黒いシャツが熱を帯びていく。これだけ温度が高いと、服を着ていることすらうざく感じられてしまう。が、健康真面目好青年の僕は法を犯したりしない。大学の駐輪場に止めてきた自転車に乗った。蝉が、路上で死んでいた。切れ味抜群の刃にやられたのか。そそくさと薄暗い部屋に戻って、シャワーを浴びた。ぐだぐだしていたら外が強烈なオレンジ色なのに気がついて、つい写真を取ってしまった。そんな夕景もあっという間に過ぎ去って、奴は刀を鞘に納めた。僕も、朝が来るまで静かに眠ろう。
四畳半夜話
君と電話をしていて、いつの間にか眠りに落ちてしまうあの夜が愛おしい。いつまでも、こうやって夜を無駄にしてしまいたいと思う。言葉を交わして、頷いて、星の光がまた一つ消える。布団はどんどん柔らかくなって、淋しい人みたいに僕の身体をきつく抱きしめる。半身から、ゆっくりと果てのないどこかへ埋もれていく。そして夢へとたどり着く。夢が朝の光でほどけるまで、僕は目を閉じて現実から浮遊する。
たった数時間でも、それはテスト勉強のために費やされた一日よりも貴重で、価値があって、本当にくだらない。僕は君のことを本当は何も知らないかもしれないし、君も僕のことを変に解釈しているかもしれない。だけど喋っているあいだはなんとなく、この惑星には僕たち二人だけ、という気分になる。世界が四畳半ぐらいまで狭くなる。そして畳の上のちゃぶ台で、いろんな話題を肴にお酒を酌み交わす。友愛のしるしに。別にハグは必要ないけれど、たまに酔っぱらって変なことを口から滑らせる。まあそれも夜のせいだから。
僕の住む町のどこか近くで君のような存在を見つけたら、君のことは忘れてしまうのだろうか。でも、僕とはほとんど何の関係のない、君だから話せることもあるような気がしている。またあの四畳半で人生のひとときを無駄にする瞬間を慈しむために、今日も明日も眠りにつき、夢を見る。歌を聴きながら、ニュースに愕然としながら。
虜
黒い点が壁をするする伝っているのに気がついて、点がじっと落ち着いたところに近づいて軽く息を吹きかけてみる。僕の悪戯にその子は驚いて、焦った様子で壁をぴょんぴょん跳ねていく。その子のことはよく知らない。勝手にやって来て、いつの間にかどこかへ消えている。そしてまた時間が経てば、違う誰かが壁を伝う。
前までクモは嫌いだった。もともと虫の類は苦手だし、あの得体のしれない感じが怖った。だけど一人暮らしを始めて、クモよりおっかない生物を見るようになって、クモに対する捉え方が変わってきた。こちらの方が図体が大きいから、という図々しさもあると思うけど、だんだんと可愛く感じられてきた。だからここ最近は、ふと壁に見つけたときは少しだけ心が弾む。可愛いお客を部屋に招いて、悪戯したりそのままほうっておいたり。あちらの方も、別にこっちに迷惑をかけたりしない。ただ生餌をさがしているだけだ。
心がふっと落ち込んで、誰かを犠牲にして夜を消費したい(それでもそんな相手がいない)とき、可愛らしいその子が現れ、無言のまま壁に止まる。触肢をさわさわ動かして、じっと一休み。それがなんだか浮袋のような安心感があって、僕は頼りない蜘蛛の糸を摑んだまま夜をすり抜ける。どこかで糸を切られて、また地獄に戻ってしまうのだけど。
思考も分からず、どこから来たのかも分からない。そもそも向こうは変温動物だ。今日だって、玄関の方で一匹、そして普通の部屋でもう一匹見つけた。前者は天井の隅で手足を伸ばし、こちらに攻撃しているみたいだった。後者は壁で静かに冷房の風を浴びていたけれど、気がつくと洗濯物の山にいた。ベランダには夏の空気、洗濯機が揺れるうるさい音。そうして午後はうららかに過ぎた。洗濯物のあの子はどこへ行っただろう。隅っこが好きな方はまだ根暗っぽく落ち着いている。またいつの日か、二人とも部屋を出て、うだるような熱気の中へ出て行くのだろう。僕は、誰でも歓迎するつもり。誰でもいいってわけじゃないけど。それからクモの足を数えて、ほんのちょっと淋しい気持ちになるのだ。